どれほど優れたBCP(事業継続計画)を作っても「机上の空論」では意味がありません。
実際に災害や障害が起きたとき、現場のメンバーが迷わず動けなければ計画は役に立たないでしょう。
そのために欠かせないのが BCP訓練 です。
なかでも手軽に始められ、かつ計画の不備を洗い出しやすい方法として注目されているのが 「机上訓練(図上演習)」 と呼ばれる訓練です。
机上訓練とは、
想定した災害シナリオをもとに関係者が集まって「もしこの状況になったらどう動くか」を話し合い、
実際の行動フローや役割分担を確認・検証する訓練のことです。
紙とペン、あるいは会議室があれば始められるため実地訓練よりも準備が簡単で、
BCPを策定したばかりの組織や定期的な見直しをしたい企業に最適です。
本記事では、
- 机上訓練の定義と目的
- 実施手順や成功させるポイント
- よくある課題と改善のヒント
- 企業・自治体の机上訓練の進行例
を解説します。
「BCPを作ったけれど、このままでいいのか不安…」という方はぜひ参考にしてみてください。
災害時に確実な安否確認を行うには、信頼できる仕組みが不可欠です。
ANPIC(アンピック)なら、誰でも簡単に使えるシステムと手厚いサポートで、初めての導入でも安心してお使いいただけます。
- 100万人超が利用
- 直感操作で導入もスムーズ
- 専任スタッフが全面サポート
- 産学連携で実現した手頃な価格
ANPICでは、実際の管理画面を操作しながら機能や使い方を体験できる無料体験版をご用意しています。 体験中にご不明な点があれば、無料でサポートも受けられるので、安心してお試しいただけます。
BCP訓練とは?
BCP訓練の定義と種類(机上訓練・実動訓練・図上演習の違い)
BCP訓練とは、策定した事業継続計画を実際に機能させるために、
関係者が参加して「緊急時にどう動くか」を確認・改善するための訓練の総称です。
BCP訓練にはいくつかの種類があります。
| 訓練の種類 | 特徴 | 例 |
| 机上訓練(図上演習) | 想定シナリオを用いて会議形式で実施。実地行動は伴わないが計画の不備を洗い出しやすい。 | 議室で地震発生後の行動をシミュレーション |
| 実動訓練 | 実際に避難したり物を動かしたりして行う。リアルな体験ができるがコストや準備が大きい。 | オフィスからの避難・拠点移動 |
| 通知・連絡訓練 | 連絡網やシステムを用いて実際に一斉連絡を試す。 | 安否確認システムでテスト送信 |
机上訓練はこれらの中でも手軽に始めやすく、計画を定期的にブラッシュアップするのに適しています。
なぜ訓練が必要なのか【計画を“絵に描いた餅”にしないため】
BCPは作成しただけでは不十分です。
計画が現場に浸透していなければ、災害時に「マニュアルがあったのに動けなかった」という状況に陥ります。
BCP を紙面や社内向けHPなどに記載して周知するだけでは、全ての関係者が実践できると考えるのは現実的でない。継続的な教育・訓練の実施が不可欠である。
と記載されています。
訓練を行うことで、
- 誰がどんな役割を担うのか明確になる
- 想定していなかった問題点が見つかる
- 関係者の意識が高まり実際の災害時に迷わず動ける
という効果が得られます。
特に机上訓練は計画の初期段階や定期的な見直しで実施しやすく、BCPを「絵に描いた餅」にしないための第一歩となります。
机上訓練(図上演習)とは
机上訓練の特徴とメリット
机上訓練(図上演習)とは、
想定した災害や事故のシナリオをもとに、会議室などで関係者が集まり「その状況で自分たちはどう動くか」
を議論しながら進める訓練です。
実際に避難や現場での行動は行わず、机上で進めることからこの名前がついています。
主なメリット
✅ 手軽に始めやすい:会議室と資料があれば実施できコストも低い。
✅ リスクを想定しやすい:複数のシナリオを短時間で検討できる。
✅ 計画の不備を発見しやすい:実際に行動をシミュレートすることで役割や連絡経路の不明確さが見えてくる。
✅ 関係者間の共通認識が得られる:部署をまたいで議論し理解を深められる。
どんな場面で活用されるのか(大規模災害・感染症・情報障害など)
机上訓練はさまざまなリスクシナリオに応用できます。
例:大規模災害シナリオ
地震発生で本社ビルが使用不可になった場合の初動対応
停電・断水時の重要業務継続手順
例:感染症シナリオ
感染者が職場に出た場合の連絡体制と在宅勤務移行の流れ
出勤制限中の業務分担と優先業務の選定
例:情報障害シナリオ
サイバー攻撃でシステム停止した場合の代替手順
顧客データへのアクセスが途絶えた際の対応方法
現実的なシナリオを設定すれば、机上訓練だけでも多くの気づきを得られます。
他の訓練との違いと併用例
机上訓練は「頭で考える・議論する」ことに特化した訓練ですが、
実動訓練や通知訓練と組み合わせるとより実践的なBCP運用が可能になります。
| 訓練の種類 | 役割 | 併用例 |
| 机上訓練 | 計画の検証・改善点の洗い出し | シナリオを議論し、実動訓練の課題を決定 |
| 実動訓練 | 実際の行動を確認・体験 | 机上訓練で決めた手順を現場で実践 |
| 通知・連絡訓練 | 連絡網・システムの動作確認 | 訓練前後で実際に一斉通知を試す |
このように、
まずは机上訓練で課題を洗い出し、次に実動訓練で検証する
という流れが効率的です。
机上訓練を行う目的
計画の不備や想定外を洗い出す
机上訓練の最大の目的は、「作成したBCPを現場目線で検証し、足りない部分を見つけること」です。
書類上は完璧に見える計画でも実際に動かす段階で問題が発覚することは少なくありません。
- 「この手順、担当者が同時に別の業務を担っていて実行できない」
- 「この代替拠点、鍵の管理は誰が?」
- 「安否確認はどのツールで?通信障害時は?」
こうした具体的な課題を事前にあぶり出し、計画書に反映できるのが机上訓練の強みです。
関係者間で共通認識を作る
BCP計画は作成者だけが理解していても意味がありません。
災害時には複数の部署・拠点が協力して動く必要があるため、
「誰が」「どんな判断で」「どう動くか」を関係者間で共有しておくことが大切です。
机上訓練を通じて、
- 部署間の情報共有を促進
- 他部署の役割を理解する
- 全員が同じ優先順位・判断基準を持てる
という効果が得られ、これにより緊急時の混乱を大幅に減らせます。
役割分担や意思決定の流れを確認する
実際の災害時、
「誰がリーダーシップを取るのか」「どの段階で経営層に報告するのか」
といった意思決定の流れが曖昧だと初動が遅れます。
机上訓練ではシナリオに沿って具体的に進めながら、
- 各役職の決定権・権限を確認
- 緊急連絡網や情報伝達ルートをチェック
- 代替人員の配置や応援要請のタイミングを検討
といった運用上のポイントを整理できます。
これにより、BCP計画が「机上の理論」から「実際に動かせる計画」へと近づきます。
机上訓練の実施手順
①シナリオ設定(想定災害・影響範囲の決定)
まずは訓練で扱うシナリオを設定します。
シナリオは「自社の業務にとって現実的かつ影響の大きいもの」を選ぶのがポイントです。
例:
平日午前、主要拠点で震度6強の地震が発生
台風で物流拠点が浸水し、1週間利用不可
サイバー攻撃で基幹システムがダウン
シナリオには発生時刻や被害状況、ライフライン停止の有無などを具体的に盛り込みます。
現実味のあるシナリオほど訓練の質が上がります。
②参加者の選定と役割確認
どのメンバーが訓練に参加するかを決めます。
経営層、各部門の責任者、現場のリーダーなど災害時に意思決定や初動を担う人を中心に選びます。
- 参加者には事前に「自分の役割」を明示しておく
- 必要に応じてオブザーバー(記録係や外部専門家)も用意する
これにより、訓練中に「自分は何をすべきか」が分かりやすくなります。
③進行方法(ファシリテーター・時間配分)
進行役(ファシリテーター)を決め、時間配分を計画します。
- ファシリテーターがシナリオを読み上げ段階的に状況を追加
- 各段階で「どう動くか」を参加者がディスカッション
- 制限時間を設けて意見を集約、問題点をホワイトボードやシートに記録
1回の訓練は30分〜2時間程度が一般的です。
長くなりすぎると集中力が落ちるため、テーマを絞ることもポイントです。
④実施中のポイント(記録、意見交換、問題点抽出)
訓練中は意見や問題点を必ず記録します。
議論を進めるうちに次のような課題が見つかるはずです。
- 「この情報、誰が集めて誰に報告するの?」
- 「代替拠点までの輸送手段が決まっていない」
- 「リーダー不在時の判断フローが曖昧」
これらをその場でホワイトボードに書き出すことで後から改善しやすくなります。
⑤訓練後のレビューとBCPへの反映
訓練後は、気づいた改善点をBCP計画に反映するレビューを行います。
- 訓練記録を整理し、良かった点・課題点をまとめる
- 改善が必要な項目をリスト化し担当者と締切を決定
- 訓練で出た新たなシナリオを次回のテーマにする
この「フィードバックを計画書に反映する」までが机上訓練の大切なプロセスです。
机上訓練を成功させるポイント
現実的かつ自社の状況に即したシナリオを作る
机上訓練でよくある失敗は、非現実的なシナリオや自社に関係の薄いテーマを選んでしまうことです。
これでは参加者が真剣に考えづらく、現場に役立つ気づきが得られません。
- 自社の立地・業務・規模に即したシナリオを選ぶ
- 実際に起こり得る災害やトラブルを想定する
- 「月曜午前9時に地震発生、主要サーバーがダウン」など時間・状況を具体的に設定する
リアルな状況を描くことで、参加者は「自分ならどう動くか」を真剣に考えやすくなります。
小規模から始めて定期的に行う
初めての机上訓練ではテーマや参加者を絞った小規模な実施がオススメです。
いきなり全社規模で行うと準備や進行が複雑になり、成果が見えづらくなります。
- まずは1拠点・1部署を対象に実施
- 課題を洗い出してから徐々に拡大
- 年1回~2回など定期的に実施して継続的な改善を図る
この積み重ねが実際の災害時に強い組織を作ります。
ファシリテーターや外部専門家の活用
机上訓練は進行役(ファシリテーター)の質で成果が変わります。
進行に慣れていない場合や初回の訓練では、外部の専門家を招くのも有効です。
- 外部コンサルタントや防災士のサポートでシナリオ作成や進行を円滑に
- ファシリテーターが適宜質問を投げて参加者の思考を深める
- 時間管理や議論の方向性をコントロールして集中度を高める
参加者全員の積極的な意見出しを促す
机上訓練は「議論の質」が成果を左右します。
一部の人だけが話すのではなく、全員が発言できる雰囲気作りが重要です。
- 発言を否定せず、どんな意見も書き留める
- 役職や年齢に関係なく意見を出しやすいよう座席や進行を工夫
- チームごとのディスカッションやロールプレイを取り入れる
全員が主体的に関わることで、実践的で多角的な改善点が見つかります。
よくある課題と改善のヒント
「想定が甘すぎて気づきが得られない」→シナリオを複数用意する
机上訓練では想定する災害や障害が漠然としていると、
「いつも通りで大丈夫だね」で終わってしまい、新たな改善点が見つからないという事態が起こります。
改善のヒント
- シナリオはより具体的なものを複数用意する
- 例えば「主要拠点の電源が48時間停止したら?」「通信網が全てダウンしたら?」など具体的に深堀り
- ファシリテーターが途中で状況を追加して参加者の想定外を引き出す
「時間が長すぎて集中力が続かない」→テーマを絞って短時間で回す
長時間にわたる訓練は参加者が疲れてしまい議論の質が落ちます。
特に初めての場合は短時間でテーマを絞るのがコツです。
改善のヒント
- 初回は1テーマにつき60~90分程度を目安に
- 複数テーマがある場合は次回以降に分けて実施
- 進行役が時間を管理し要点だけを深堀りする
「実施後に改善が進まない」→結果をBCPに必ずフィードバックする
訓練をやりっぱなしにするとせっかくの気づきが活かされず、計画書がアップデートされないままになってしまいます。
改善のヒント
- 訓練終了後に「改善点リスト」と「担当者・期限」を明確化
- 訓練結果を次回の机上訓練のテーマに反映
- 社内会議や経営層への報告で改善計画を共有する
企業・自治体の机上訓練の進行例
【製造業】台風による物流拠点の停止
シナリオ:主要倉庫が浸水し、出荷が1週間止まった場合
訓練実施後の課題:
- 代替倉庫の契約が未整備だった
- 部門間の情報共有ルートが不明確だった
- 緊急時の優先出荷品目を事前に決めていなかった
改善計画:
- 代替拠点契約の締結
- 部門を横断した連絡網の整備
【大学】地震発生時の安否確認と授業継続・安否確認体制の検証
シナリオ:平日の午前中に震度6の地震が発生し、通信が一部途絶
訓練実施後の課題:
- 安否確認システムの操作手順が一部で理解されていなかった
- 教室ごとの避難ルートの周知が不足していた
- オンライン授業への切り替え準備が不十分だった
改善計画:
- 全学的なマニュアルの更新
- 教職員への再教育し初動対応力を高める
【自治体】地域全体の避難所運営
シナリオ:大規模地震で複数の避難所が開設されたが、物資が不足している
訓練実施後の課題:
- 避難所間で物資情報を共有する仕組みがない
- 高齢者・要配慮者の支援フローが曖昧
- 担当者が重複し意思決定が滞る場面があった
改善計画:
- 物資管理システムの導入
- 役割分担表の見直し
災害時に確実な安否確認を行うには、信頼できる仕組みが不可欠です。
ANPIC(アンピック)なら、誰でも簡単に使えるシステムと手厚いサポートで、初めての導入でも安心してお使いいただけます。
- 100万人超が利用
- 直感操作で導入もスムーズ
- 専任スタッフが全面サポート
- 産学連携で実現した手頃な価格
ANPICでは、実際の管理画面を操作しながら機能や使い方を体験できる無料体験版をご用意しています。 体験中にご不明な点があれば、無料でサポートも受けられるので、安心してお試しいただけます。
まとめ|机上訓練でBCPを「動かせる計画」にする
BCP(事業継続計画)は作成しただけでは「絵に描いた餅」に過ぎません。
緊急時に本当に役立つ計画にするには、計画を動かしてみる=訓練することが欠かせません。
その第一歩として最も実施しやすいのが 机上訓練(図上演習) です。
会議室とシナリオさえあれば始められ、参加者全員で話し合うことで次のような効果が得られます。
✅ 計画書の不備や想定外を事前に発見できる
✅ 部署や役職を超えた共通認識を形成できる
✅ 役割分担・意思決定の流れを事前に確認できる
さらに、訓練で得た気づきを BCP計画書にフィードバックし定期的に見直す ことで、
計画はより実践的なものへと進化します。
「BCPを作ったけれどこれで本当に大丈夫だろうか?」と感じているなら、
まずは小規模な机上訓練から始めてみてください。
机上訓練を繰り返すことで組織は「もしも」に強くなり、従業員や顧客を守る力が着実に高まります。
出典:内閣府『事業継続ガイドライン -あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-』
(令和5年3月)
第6章「事前対策及び教育・訓練の実施」6.2.1節(p.27)
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline202303.pdf

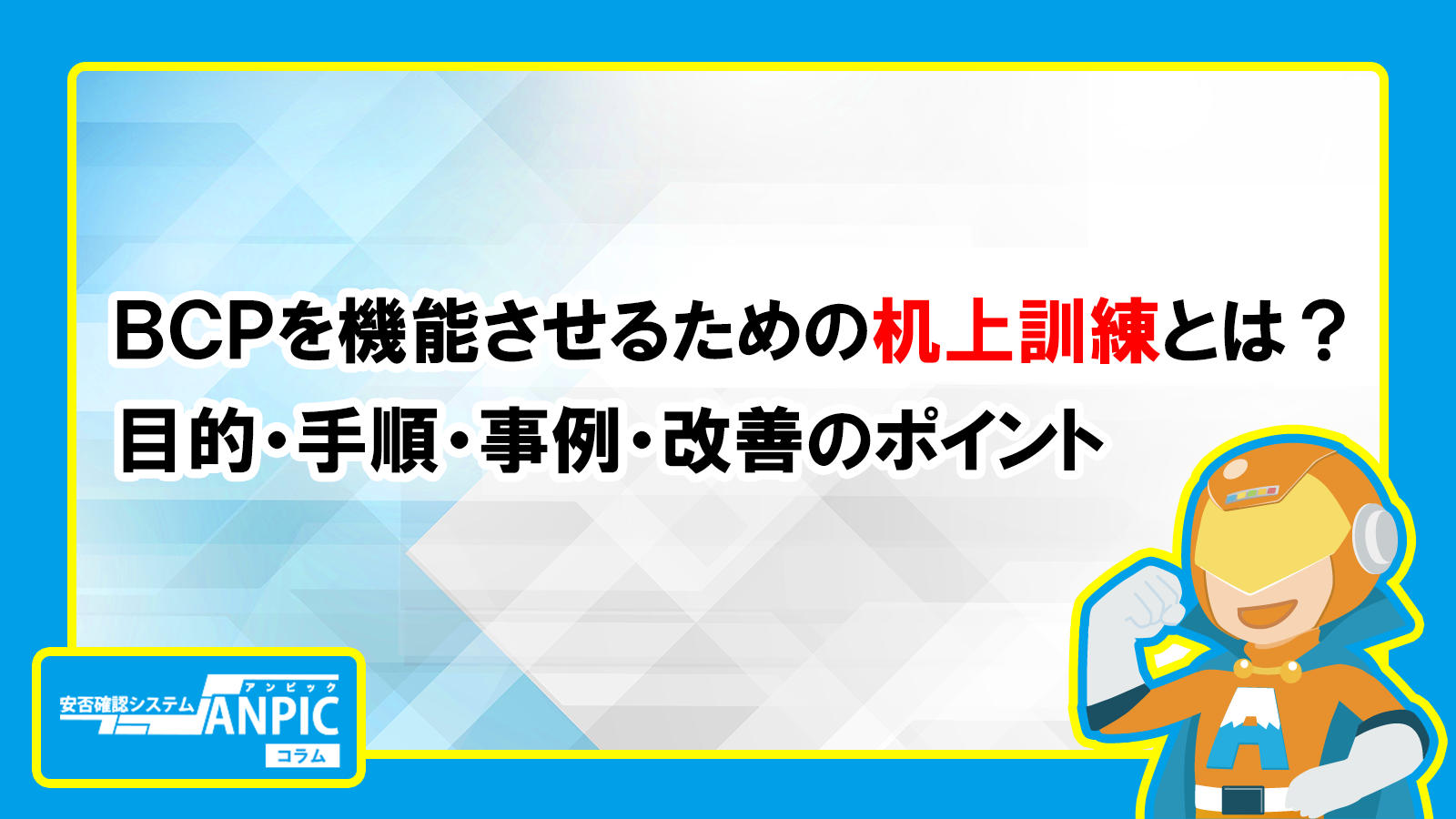

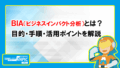

コメント