地震や台風、豪雨、さらには感染症やサイバー攻撃──
私たちの社会は、いつどこで事業継続を脅かすリスクに直面するかわかりません。
実際、内閣府の防災情報によれば、近年の大規模災害やパンデミックによって
「多くの企業が業務停止や取引縮小を経験し、信用を失う事例があった」と報告されています。
こうした状況で注目されているのが、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画) です。
BCPは、内閣府のガイドラインで「災害や事故が発生した際に、重要業務を中断しない、または短時間で再開させることで、取引先の流出や信用低下を防ぐ経営戦略」と定義されています。
つまりBCPは、単なる防災マニュアルではなく、
組織が人命・資産・信用を守り、社会的責任を果たすための“経営の基本戦略” です。
中小企業庁が示す「BCP策定運用指針」でも、
「従業員とその家族の生命や健康を守り、事業継続によって顧客の信用と地域経済の活力を守る」
ことがBCPの目的とされています。
本記事では、BCPの定義や目的から、策定の手順、運用のポイント、そして最新の動向まで、
これからBCPを学びたい方や、社内で導入を検討する担当者の方に向けて、網羅的に解説していきます。
災害時に確実な安否確認を行うには、信頼できる仕組みが不可欠です。
ANPIC(アンピック)なら、誰でも簡単に使えるシステムと手厚いサポートで、初めての導入でも安心してお使いいただけます。
- 100万人超が利用
- 直感操作で導入もスムーズ
- 専任スタッフが全面サポート
- 産学連携で実現した手頃な価格
ANPICでは、実際の管理画面を操作しながら機能や使い方を体験できる無料体験版をご用意しています。 体験中にご不明な点があれば、無料でサポートも受けられるので、安心してお試しいただけます。
BCP(事業継続計画)とは何か
BCPの定義と目的
BCPとは Business Continuity Plan(事業継続計画) の略称です。
災害や事故、システム障害、感染症の流行などの緊急事態が発生した際に、
重要な業務を中断させない、あるいは短期間で再開させるための計画 を指します。
内閣府の「事業継続ガイドライン(2023年改訂版)」では、BCPを次のように定義しています。
「災害や事故が発生した際に、重要業務を中断させない、または短時間で再開することにより、顧客や取引先の流出を防ぎ、信用低下を回避する経営戦略。」
つまり、BCPは単なる防災マニュアルではなく、
人命・資産・取引先を守るための、経営に直結する計画 なのです。
防災計画との違い
「防災計画」と「BCP」は混同されがちですが、目的や範囲が異なります。
| 項目 | 防災計画 | BCP(事業継続計画) |
| 主な目的 | 災害発生時の被害を最小限に抑える | 重要業務を止めず、または早期に再開させる |
| 対象範囲 | 従業員の避難誘導、建物の安全確保など | 人員・設備・情報を活用し業務を継続する仕組み |
| 視点 | 人命・施設保護中心 | 経営の継続・信用維持中心 |
東京都防災サイトでも、「従来の防災計画に加えて、優先業務を特定し、短時間で復旧するための方法を準備する必要がある」と明記されています。
つまり、防災計画が「守る」ための計画であるのに対し、BCPは「守った後、事業を続ける」ための計画と言えます。
BCPが求められる背景(災害・パンデミック・サイバーリスクなど)
近年、BCPが強く求められる背景には、次のような現実的なリスクの増大があります。
自然災害の激甚化
地震・台風・豪雨といった災害は毎年のように発生し、被害規模も拡大しています。
感染症パンデミック
新型コロナウイルス流行では、多くの企業や大学が出社・登校できない状況に陥り、BCPの有無で対応力に大きな差が出ました。
サプライチェーンリスク
グローバル化が進む中、ひとつの拠点が止まると世界中で調達・供給が滞るリスクが高まっています。
サイバー攻撃やシステム障害
情報インフラが止まれば、業務はたちまち中断します。BCPでは、こうしたリスクを想定し代替策を考えておくことが重要です。
これらの背景から、BCPは大企業だけでなく、中小企業や大学などあらゆる組織にとって必須の取り組みとなっています。
中小企業庁の指針でも「地域経済の活力を守るために、各組織が自らBCPを策定・運用することが求められる」と強調されています。
BCPを策定するメリットと必要性
なぜ企業・団体にとって必須なのか
BCPは、単なる「やったほうがいい備え」ではなく、
企業や大学が生き残るための必須条件になりつつあります。
大規模災害やシステム障害が起きた際、
「従業員や拠点の被害状況がわからず業務が停止したまま数日が過ぎた」
という事例は少なくありません。
内閣府の調査でも、BCPを策定していなかった企業の多くが災害後に取引停止や信用低下を経験したと報告されています。
逆に、平時からBCPを策定していた企業は、
復旧スピードが速く、顧客との契約維持に成功している例が多く見られます。
大学でも、オンライン授業や代替キャンパス運用などを想定したBCPがあれば、学生の学びを止めずに済みます。
取引先や顧客からの信頼維持
BCPを整備していることは、社外から信頼を得るための証明になります。
取引先:
「もしものときにも納品やサービスを継続できる企業」として選ばれやすくなります。
顧客・学生・保護者:
「災害時でも責任を果たせる組織」という評価につながり、ブランド価値を高めます。
中小企業庁の「BCP策定運用指針」でも、「事業継続計画を策定し、実践することは、取引先の信頼を確保し、顧客や地域社会の期待に応えることにつながる」と明記されています。
法令・ガイドライン上の位置づけ(内閣府や中小企業庁の指針)
BCP自体を義務付ける法律は現状ありませんが、
国や自治体はガイドラインを通じて積極的な策定を推奨しています。
内閣府 事業継続ガイドライン
BCPを「経営戦略の一環」として位置付け、経営層が率先して取り組むべきと強調。
中小企業庁 BCP策定運用指針
企業規模にかかわらず「身の丈にあったBCP」を段階的に導入することを推奨。
一部業種では策定が事実上の前提
金融機関との取引や入札参加要件などで、BCPの有無が評価項目になるケースが増えています。
このように、BCPは法的義務ではないものの、
経営における社会的責任の一部として、国の指針でも強く求められています。
BCP策定の基本ステップ
現状分析・リスク評価
BCPの第一歩は、自組織の現状を正しく知ることです。
内閣府「事業継続ガイドライン」では、まず「リスク評価」と「業務影響分析(BIA)」を実施するよう推奨しています。
・どんな災害・事故・障害が起こり得るか
・各拠点・各業務が停止した場合の影響はどれほどか
・被害が出たときの資源(人員・設備・情報)の脆弱性はどこにあるか
こうした現状把握とリスク評価を通じて、自社にとって本当に守るべき重要業務が見えてきます。
重要業務の特定と優先順位付け
リスク評価の次は、「絶対に止めてはいけない業務」を決める段階です。
中小企業庁の指針では、これを「重要業務の特定」と呼び、
「顧客・取引先への影響が大きく、短時間で復旧が必要な業務」を優先して検討するよう推奨しています。
例:
製造業なら「基幹生産ライン」
大学なら「学生・教職員への連絡、授業提供」
医療機関なら「緊急診療体制」
重要業務を決めることで、限られたリソースをどこに集中すべきか明確になります。
復旧目標時間(RTO)・許容停止時間(MTPD)の設定
BCPでは、重要業務ごとに
「どのくらいの時間で復旧させる必要があるか」 を定めます。
RTO(目標復旧時間):停止してから復旧するまでの目標時間
MTPD(最大許容停止時間):この時間を超えると事業存続に致命的な影響が出る時間
内閣府のガイドラインでも、RTO・MTPDの設定を計画の要と位置づけています。
この数値を基準に、設備や人員の配置を考えます。
代替手段・リソースの検討
重要業務を短時間で復旧させるには、代替手段や予備リソースを用意する必要があります。
たとえば──
・別拠点での操業やテレワーク体制の構築
・予備サーバー・バックアップ回線の確保
・代替調達先の契約
こうした準備は「いざ」というときに大きな差となります。
計画の文書化と社内周知
検討した内容をBCPとして文書化し、全社員がアクセスできるようにします。
さらに、役員・管理職・現場担当者まで、自分の役割が分かる状態に周知することが欠かせません。
中小企業庁の指針でも、計画策定後の社内展開を重要項目として挙げています。
BCPを機能させるための運用ポイント
定期的な訓練・シミュレーション
BCPは「作っただけ」では意味がありません。
実際に災害が起きたときに動かせるように、定期的な訓練とシミュレーションが必要です。
内閣府の「事業継続ガイドライン」でも、「計画を作成するだけでなく、訓練・教育を通じて従業員が実際に動ける体制を確保すること」と明記されています。
例えば年1回、震災を想定した初動訓練を行うことで、
連絡手段や役割分担の不備が明らかになり、平時に改善できます。
組織全体への意識浸透と教育
BCPは経営層だけが知っていても機能しません。
現場の社員、各部署の責任者、そして新入社員に至るまで、
「自分がどんな役割を担うのか」を理解している必要があります。
そのために、
・定期的な社内研修の実施
・マニュアルやチェックリストの配布
・全社向けポータルサイトでの情報共有
といった取り組みを継続することが大切です。
PDCAサイクルによる計画の更新・改善
BCPは一度作ったら終わりではなく、定期的に見直すべき計画です。
新しい設備導入や拠点増設、テレワークの拡大など、
組織を取り巻く環境は変化し続けます。
Plan(計画):現状に合わせた計画を策定
Do(実行):訓練・教育を実施
Check(評価):訓練結果や災害時の対応を検証
Act(改善):問題点を反映してBCPを改訂
このサイクルを回すことで、常に実効性の高いBCPを維持できます。
サプライチェーンや取引先との連携
BCPは自社だけで完結しません。
取引先や協力会社が業務停止すると、サプライチェーン全体が止まる可能性があります。
内閣府のガイドラインでも、「主要取引先と事業継続に関する情報を共有し、連携を図ること」
が推奨されています。
・主要取引先と「緊急時の連絡網」を構築
・調達先や物流ルートの二重化
・重要顧客への代替サービスの事前提案
こうした外部連携も、BCPを機能させるためには欠かせません。
BCP策定時によくある課題と解決のヒント
計画はあるが実践できないケース
多くの企業が直面する課題のひとつが、
「BCPは作成したが、いざという時に動かせる自信がない」という状況です。
原因としては、
・現場が内容を知らない・役割が不明確
・訓練をしていないため、手順が頭に入っていない
・連絡手段や代替手段が実際には機能しない
などが挙げられます。
解決のヒント:
・訓練を定期的に行い、計画を「動かす練習」をする
・訓練後のフィードバックを反映して改善する
・全社員が閲覧できるようにBCPを共有する
拠点ごとの状況差に対応するには
拠点が複数ある企業や、キャンパスが分かれている大学では、
「本社・本部の計画だけでは現場対応が間に合わない」という課題が生じがちです。
地域によって想定されるリスクやインフラ状況が違うため、
一律のBCPでは不十分です。
解決のヒント:
・各拠点で独自の初動計画や連絡網を持つ
・全体計画と拠点計画をリンクさせ、情報共有を密にする
・拠点ごとの訓練を実施し、現場課題を吸い上げる
中小企業や教育機関でのリソース不足への対応
「人手が少なくてBCPまで手が回らない」「予算が取れない」
──こうした声もよく聞かれます。
中小企業庁の指針でも、「BCPは完璧を目指すのではなく、身の丈に合った計画から始めること」
と明記されています。
解決のヒント:
・まずは最重要業務だけに絞って計画を立てる
・無料で利用できる公的テンプレートやマニュアルを活用する
・自治体や商工会議所が開催するBCPセミナーや支援制度を活用する
小さく始め、段階的に計画を拡張していくことで、
リソースが限られた組織でも現実的なBCP策定が可能です。
BCPの最新動向と今後の課題
テレワーク・クラウド活用時代のBCP
新型コロナウイルスの流行を経て、
「どこでも働ける仕組み」 がBCPの重要要素として定着しました。
内閣府の「事業継続ガイドライン(2023年改訂版)」でも、「クラウドやテレワーク環境の整備は、パンデミックや大規模災害時に事業を継続させる上で有効」と記載されています。
・オフィスが使えなくても業務を続けられるリモート体制
・データをクラウドに保管し、どこからでもアクセス可能にする仕組み
・VPNや多要素認証など、セキュリティを確保した通信環境
こうした技術活用は、現代のBCP策定に欠かせない視点です。
感染症対策や気候変動への対応
BCPがカバーすべきリスクも変化しています。
これまで主に自然災害を想定していたBCPですが、
・新型コロナウイルスなどの感染症
・猛暑・豪雨といった気候変動リスク
といった、長期的かつ広域的な影響にも対応する必要があります。
感染症対応としては、
・感染拡大を防ぐ出勤制限や在宅勤務のマニュアル化
・職場の分散運営
・従業員の健康情報管理
気候変動対応としては、
・停電・断水などインフラ障害を想定した代替策
・熱中症リスクを考慮したシフト・勤務形態の見直し
などが求められています。
国や自治体が提供する支援制度・補助金
BCP策定を後押しするため、国や自治体はさまざまな支援を用意しています。
中小企業庁の「BCP策定運用指針」
無料で使えるひな型やチェックリストを公開
👉 中小企業庁BCPページ
地方自治体の助成金・補助金
たとえば東京都では、BCP策定や訓練費用の一部を補助する制度を実施しています。
セミナー・相談窓口
商工会議所や地域産業振興センターが、無料の相談会や講習会を定期開催
これらを活用することで、費用やノウハウの不足を補いながらBCPを整備することができます。
まとめ|BCPは「組織を守る基本戦略」、今こそ計画と運用を見直そう
BCP(事業継続計画)は、
「災害や事故が起きても、重要業務を中断させない・短時間で再開させる」ための経営戦略です。
内閣府や中小企業庁のガイドラインでも、「顧客や取引先の流出を防ぎ、信用低下を回避するため、組織の規模を問わず取り組むべきもの」と位置づけられています。
本記事でご紹介したように、BCPは以下を柱として成り立ちます。
・現状分析とリスク評価を行い、守るべき重要業務を特定する
・復旧目標時間(RTO)や代替手段を設定し、計画を文書化する
・訓練・教育・PDCAサイクルを通じて、計画を常に実効性のあるものにする
・サプライチェーンや取引先との連携、テレワークやクラウド活用など、時代に合わせて進化させる
これらを実践することで、
災害やパンデミックといった不測の事態でも、
「人命を守り、事業を守る」組織として社会からの信頼を維持することができます。
もしまだBCPを策定していない、あるいは何年も見直していないという場合は、
今こそ計画と運用を点検・更新する絶好のタイミングです。
公的機関が提供するガイドラインや支援策を活用しながら、
自組織に合ったBCPを整備し、未来に備えましょう。
災害時に確実な安否確認を行うには、信頼できる仕組みが不可欠です。
ANPIC(アンピック)なら、誰でも簡単に使えるシステムと手厚いサポートで、初めての導入でも安心してお使いいただけます。
- 100万人超が利用
- 直感操作で導入もスムーズ
- 専任スタッフが全面サポート
- 産学連携で実現した手頃な価格
ANPICでは、実際の管理画面を操作しながら機能や使い方を体験できる無料体験版をご用意しています。 体験中にご不明な点があれば、無料でサポートも受けられるので、安心してお試しいただけます。

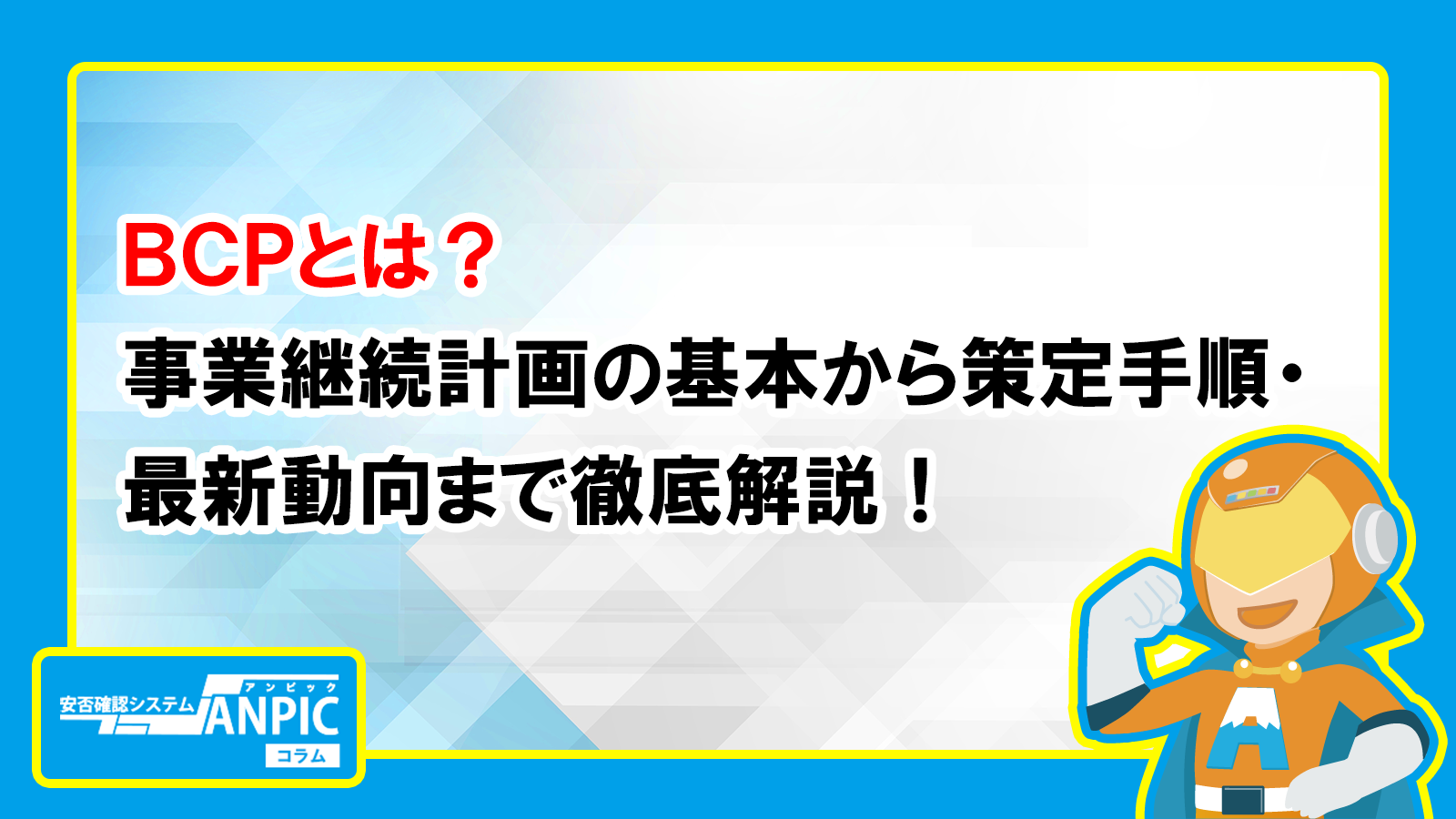

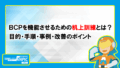

コメント