BCP(事業継続計画)を作る際、
「どの業務を最優先で守るべきか」「どれくらいの時間で復旧させるべきか」を決めるのは、非常に重要なステップです。
その判断を支えるのが BIA(Business Impact Analysis:ビジネスインパクト分析) です。
BIAとは各業務が停止した場合にどんな影響が出るのかを分析し、重要業務の優先度や必要資源を“見える化”する手法のことです。
内閣府の事業継続ガイドラインでも、BCP策定の初期段階で「業務影響分析(BIA)の実施」を強く推奨しています。
たとえば、
「この業務が1日止まると売上にどれくらい影響する?」
「この部署が機能しないと、どんな顧客対応が滞る?」
といった観点で分析を進めることで、復旧目標時間(RTO)や最大許容停止時間(MTPD)を設定し
限られた経営資源を効率的に配分できるBCPを作れるようになります。
本記事では、
- BIAの定義と目的
- 実施のステップとポイント
- よくある課題と改善策
- BCPへの活かし方
を初めての担当者でも理解できるよう、わかりやすく解説します。
これからBCPを強化したい方は、ぜひ参考にしてください。
災害時に確実な安否確認を行うには、信頼できる仕組みが不可欠です。
ANPIC(アンピック)なら、誰でも簡単に使えるシステムと手厚いサポートで、初めての導入でも安心してお使いいただけます。
- 100万人超が利用
- 直感操作で導入もスムーズ
- 専任スタッフが全面サポート
- 産学連携で実現した手頃な価格
ANPICでは、実際の管理画面を操作しながら機能や使い方を体験できる無料体験版をご用意しています。 体験中にご不明な点があれば、無料でサポートも受けられるので、安心してお試しいただけます。
BIA(ビジネスインパクト分析)とは?
BIAの定義とBCPとの関係
BIA(Business Impact Analysis:ビジネスインパクト分析) とは、
組織の各業務が中断した場合に、どの程度の影響(インパクト)が生じるかを分析し、
優先すべき重要業務と必要な復旧時間を明確にする手法 です。
内閣府「事業継続ガイドライン」では、BIAについて次のように説明しています。
事業の中断による、業務上や財務上の影響を確認するプロセスのこと。重要な事業・業務・プロセス及びそれに関連する経営資源を特定し、事業継続に及ぼす経営等への影響を時系列に分析を行う。
つまり、BIAは BCP(事業継続計画)の土台 となるプロセスです。
もしBIAがないままBCPを作ってしまうと、「何を最優先で復旧すべきか」「どれくらいの時間で戻すべきか」が曖昧になり、実際の災害時に有効な行動を取れなくなります。
なぜBIAが必要なのか
組織にはさまざまな業務がありますが、すべてを同じレベルで守るのは不可能です。
限られた人員・資源・時間をどこに集中させるかを決めるためには、
「業務ごとの影響度を数値や優先度で可視化」する必要があります。
BIAを行うと次のようなことが分かります。
- どの業務が中断すると売上や顧客に大きな影響を与えるか
- どの業務は停止しても数日なら許容できるか
- 各業務を支える人員・設備・ITシステムは何か
これにより、BCPで定める「復旧の順番」や「必要なバックアップ手段」を的確に決められます。
防災計画・リスク分析との違い
BIAは単なる防災計画やリスク分析とは異なります。
| 手法 | 主な目的 | 特徴 |
| BIA | 業務停止時の影響度を分析し、優先業務を決定する | 復旧目標時間(RTO)や資源を特定 |
| 防災計画 | 災害時の被害を最小化する | 避難計画や設備対策が中心 |
| リスク分析 | 起こりうるリスクを洗い出す | 発生確率や影響度を評価 |
防災計画やリスク分析が「備えを整える視点」であるのに対し、
BIAは「業務を止めない・早く戻すための戦略を決める視点」で行われます。
この違いを理解することで、BCPの中でBIAが果たす役割がより明確になります。
BIAの目的とメリット
業務ごとの影響度を「見える化」できる
BIAの最大の目的は業務が止まった場合の影響度を明確にすることです。
どの業務がどれだけの売上・顧客・社会的信用に影響するのかを可視化することで、
経営層や現場が共通認識を持てるようになります。
たとえば──
- 物流部門が1日止まるとどれくらいの出荷遅延が発生するか
- コールセンターが機能停止すると顧客対応や契約にどれほどの影響が出るか
こうした具体的な数値や想定をもとに議論できるようになるのが、BIAの大きな強みです。
経営資源の優先順位を決めやすくなる
災害や障害時にはすべての業務を同時に守ることは困難です。
限られた人員や予算をどこに集中させるかを決める際、BIAがその判断材料になります。
- 最も影響の大きい業務を最優先で復旧
- 優先度の低い業務は一時停止や後回しにする
- 必要なリソース(人員・設備・IT)を効率的に割り振る
このように、BIAは「どの業務を何時間以内に再開するか」という戦略を練る土台となります。
BCP計画の精度を高め、無駄を減らす
BIAを実施するとBCPの内容がより現実的で効果的なものになります。
逆にBIAを行わないままBCPを作ると、
- 必要以上の設備投資やバックアップを用意してしまう
- 本当に重要な業務の復旧が遅れる
といったリスクが高まります。
BIAを通じて重要業務とその優先度を正確に把握すれば、
限られた予算や人材を無駄なく活用し、実践的なBCPを構築することが可能です。
BIAの基本ステップ(実施手順)
① 対象範囲・前提条件の設定
まずは BIAをどの範囲で行うのか を決めます。
- 全社で行うのか、主要拠点や特定部門に絞るのか
- 災害の種類や想定規模をどう設定するのか(例:震度6強の地震、3日間の停電など)
この段階で前提条件を明確にしておくと後の分析がスムーズです。
② 業務の洗い出しと優先度評価
次に組織の業務をリストアップし各業務が停止した場合の影響度を評価します。
評価項目の例:
- 売上への影響(1日停止で〇円の損失)
- 顧客対応の重要度(停止が続くと信用失墜の恐れがあるか)
- 法令順守の観点(停止すると法的リスクが発生するか)
この評価をもとに、業務ごとに優先順位をつけていきます。
③ 復旧目標時間(RTO)・最大許容停止時間(MTPD)の設定
優先度を決めたら各業務について
- RTO(目標復旧時間):停止後、何時間以内に復旧すべきか
- MTPD(最大許容停止時間):これ以上止まると致命的な影響が出る時間
を設定します。
例:
- コールセンター業務 → RTO:8時間以内/MTPD:24時間
- 生産ラインA → RTO:24時間以内/MTPD:72時間
この設定が、後のBCP計画(代替手段やリソース配分)に直結します。
④ 重要業務と必要資源の特定
設定したRTOやMTPDをもとに最優先で守るべき重要業務を決め、その業務を維持するために必要な資源を洗い出します。
- 必要な人員・スキル
- 必要な設備・システム
- 必要な外部調達先や協力会社
これにより具体的なBCP施策(予備人員の配置、代替拠点の確保など)が見えてきます。
⑤ 結果の集計・レポート化
最後に、分析結果をレポートや一覧表にまとめて関係者で共有します。
- 優先業務とそのRTO・MTPD
- 業務ごとの影響度評価
- 必要資源リストと改善策の方向性
このレポートがBCP計画書に反映され、実務での意思決定の基礎資料となります。
BIA実施のポイントとよくある課題
各部署からの正確な情報収集がカギ
BIAでは現場の実態を反映したデータが不可欠です。
経営層や危機管理担当者だけで進めると、実際の業務フローや資源の使われ方が抜け落ちてしまうことがあります。
ポイント
- 各部門へのヒアリングやアンケートを実施する
- 日常業務の流れや課題を細かく確認する
- 可能ならワークショップ形式で現場の声を集める
これにより、計画が机上の理論だけではない実務に即したものになります。
「平常時の業務フロー」を可視化する方法
業務の影響度を分析するには、平常時にどのような業務がどんな順序で行われているかを可視化する必要があります。
可視化には業務フローチャートやプロセスマップを活用すると効果的です。
例
- 受注→在庫確認→出荷→請求といった流れを図式化
- 各工程で必要な人員やシステムを明記
- どの工程が停止すると全体に影響するかを洗い出す
集めたデータをどう評価・優先付けするか
情報を集めただけではBCPの優先度決定に役立ちません。
影響度を定量化・定性的に整理し、優先付けするプロセスが必要です。
ポイント
- 評価基準を統一する(売上損失、顧客影響、法的リスクなど)
- 数値化できるものは数値化し、できないものはランク付けで判断
- 経営層と現場が合意できるよう評価会議を実施する
よくあるつまずき例と解決のヒント
| よくある課題 | 解決のヒント |
| 部署ごとに情報粒度がバラバラ | ヒアリングシートや統一フォーマットを用意する |
| 想定シナリオが現実離れしている | 過去の災害・障害事例を参考に現実的な条件にする |
| 分析後、BCPに反映されない | BIA結果をBCP策定チームで必ずレビューして改善に落とし込む |
BIAは一度で完璧にする必要はありません。
初回は大まかでも良いので実施し、PDCAを回して精度を上げることが重要です。
BIA結果をBCPに活かす方法
優先業務に合わせた復旧計画の作り方
BIAで得た「重要業務と影響度の情報」は、BCPの中で 復旧計画を具体化する材料 になります。
- 優先度の高い業務は、復旧までの詳細な手順やバックアップ方法を明記
- 優先度の低い業務は、停止期間を長めに設定してリソースを集中
- 業務ごとに目標復旧時間(RTO)を基準にスケジュールを作成
こうすることで緊急時にどの業務を何時間以内に再開すべきかが明確になり、現場の混乱を防げます。
代替拠点・代替手段の検討
BIAをもとに、業務を維持するための代替手段を具体的に検討します。
- 拠点が使えない場合の代替拠点やサテライトオフィス
- IT障害時のバックアップサーバーやクラウド活用
- 人員不足時の他部署からの応援要請や外注化
重要業務ごとに「どこで」「誰が」「どのシステムで」実行するかをBCPに記載しておくと、復旧の初動が早まります。
経営層・現場への共有と教育
BIAの結果をBCPに反映したら、関係者全員が内容を理解している状態を作ることが重要です。
- 社内研修やワークショップで重要業務や優先度を共有
- 役割分担を明記したマニュアルを配布
- 訓練(机上訓練や実動訓練)でBCPに沿った動きを実践
BCPは計画書を作っただけでは意味がありません。
BIAで得た情報を全社的に浸透させることで、緊急時に計画が「生きた指針」として機能します。
災害時に確実な安否確認を行うには、信頼できる仕組みが不可欠です。
ANPIC(アンピック)なら、誰でも簡単に使えるシステムと手厚いサポートで、初めての導入でも安心してお使いいただけます。
- 100万人超が利用
- 直感操作で導入もスムーズ
- 専任スタッフが全面サポート
- 産学連携で実現した手頃な価格
ANPICでは、実際の管理画面を操作しながら機能や使い方を体験できる無料体験版をご用意しています。 体験中にご不明な点があれば、無料でサポートも受けられるので、安心してお試しいただけます。
まとめ|BIAは「BCPの土台」まずは業務影響を見える化しよう
BCP(事業継続計画)を本当に役立つものにするためには、
「何を優先して守るべきか」「どれくらいの時間で復旧させるべきか」を明確にすることが欠かせません。
その土台となるのが BIA(ビジネスインパクト分析) です。
BIAを実施することで、
- 業務ごとの影響度が見える化される
- 重要業務や必要資源が明確になる
- 復旧目標時間(RTO)や最大許容停止時間(MTPD)が設定できる
- 結果をBCPに反映すれば、計画の実効性が大幅に高まる
といったメリットが得られます。
まだBIAを実施したことがない組織も、まずは範囲を絞って小さく始め、
ヒアリングやフローチャート作成を通じて業務を見える化することからスタートしてみてください。
BIAの積み重ねがいざというときに強い組織を作る最も確実な一歩となります。
出典:内閣府『事業継続ガイドライン -あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-』
(令和5年3月)
第3章「分析・検討」3.1節(p.11)
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline202303.pdf

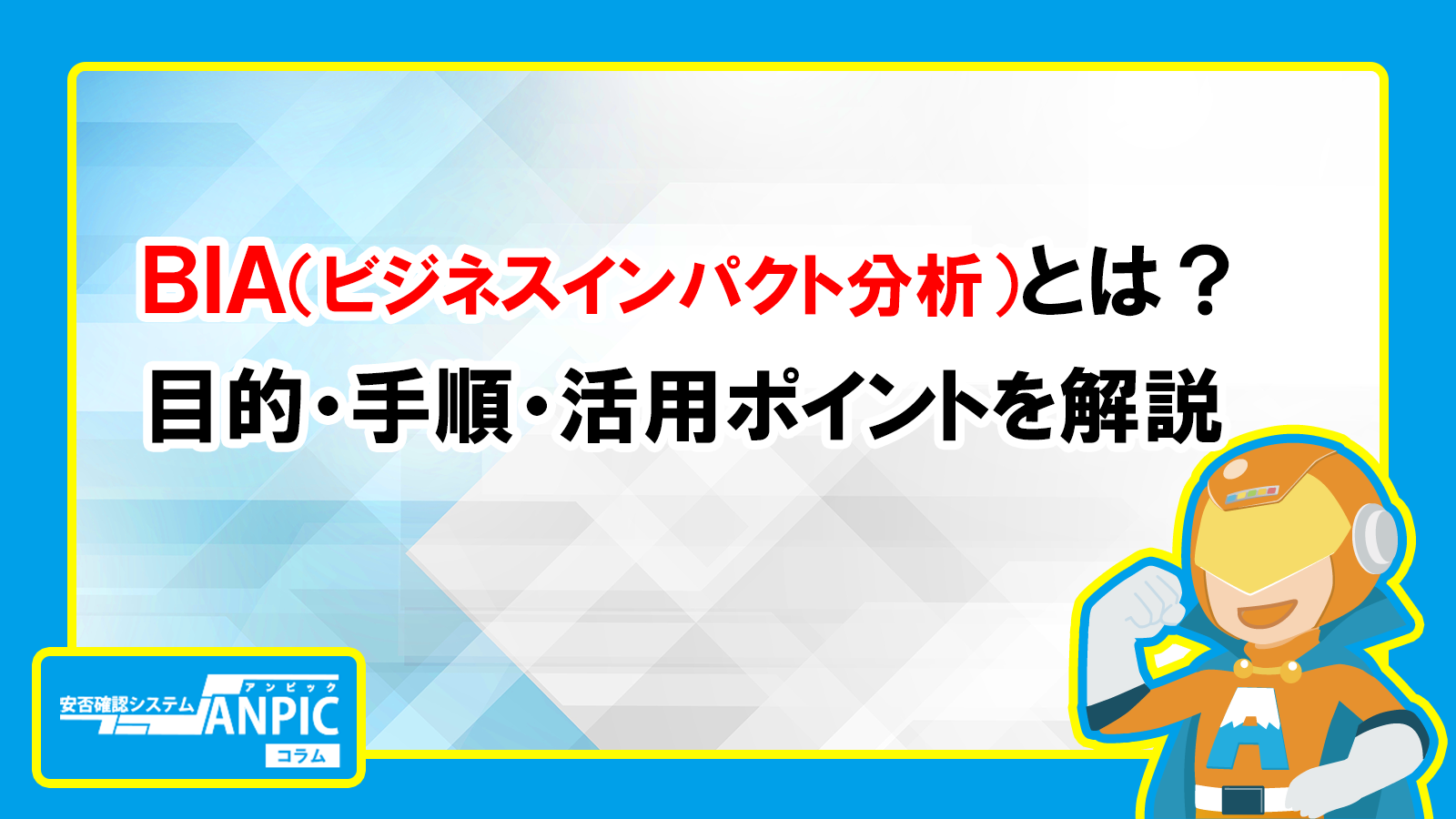

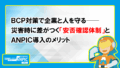
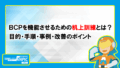
コメント