企業活動や学校運営を続けるうえで、地震・台風・豪雨・感染症など、さまざまなリスクが現実のものとなっています。
こうした緊急事態に直面したとき、「どれだけ早く重要な業務を再開できるか」 が、組織の信用や存続を左右します。
その備えとして策定されるのが BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画) です。
そしてBCPを実際に運用するための形に落とし込んだものが、「BCP事業計画書」 です。
しかし、いざ計画書を作ろうと思っても、
「どんな項目を盛り込めばよいのか分からない」「ひな形はどこで入手できるのか」と悩む担当者は少なくありません。
中小企業庁や自治体では、無料で利用できるひな形やテンプレートを公開しており、
これを活用することで、抜け漏れのない計画書を効率よく作成することができます。
本記事では下記内容について一通りご説明します。
これからBCP計画書を作成する方はもちろん、既存の計画を見直したい方もぜひ参考にしてください。
災害時に確実な安否確認を行うには、信頼できる仕組みが不可欠です。
ANPIC(アンピック)なら、誰でも簡単に使えるシステムと手厚いサポートで、初めての導入でも安心してお使いいただけます。
- 100万人超が利用
- 直感操作で導入もスムーズ
- 専任スタッフが全面サポート
- 産学連携で実現した手頃な価格
ANPICでは、実際の管理画面を操作しながら機能や使い方を体験できる無料体験版をご用意しています。 体験中にご不明な点があれば、無料でサポートも受けられるので、安心してお試しいただけます。
BCP(事業継続計画)とは?
BCPの基本概念と目的
BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、
災害や事故、感染症流行などの緊急事態が発生した際に、重要な業務を中断させない、あるいは短期間で再開させるための計画 を指します。
内閣府の「事業継続ガイドライン」では、BCPを次のように定義しています。
「災害や事故が発生した際に、重要業務を中断させない、または短時間で再開させ、情報漏洩や取引先の信用低下を防ぐための経営戦略」
BCPの目的は、組織の存続と社会的責任を果たすことにあります。
そのために、次のような取り組みが重要です。
✅ 従業員や顧客の安全を守る
✅ 顧客や取引先の信頼を維持する
✅ 経営資源(人・モノ・情報)を守る
防災計画との違い
BCPと似た言葉に「防災計画」がありますが、両者は目的が異なります。
| 項目 | 防災計画 | BCP(事業継続計画) |
| 主な目的 | 人命・設備を守る | 重要業務を止めない・早期復旧 |
| 内容 | 避難訓練や建物耐震化など | 業務継続の手順や代替策の整備 |
| 対応範囲 | 災害発生時の被害軽減 | 発生後の事業維持と再開 |
東京都防災サイトでも、
「従来の防災計画に加え、優先業務を特定し短時間で復旧できる方法を準備することが必要」
と明記されています。
なぜ今、BCP事業計画書が必要なのか
近年、BCPの重要性はますます高まっています。
・自然災害の激甚化
地震や台風の被害が年々大きくなり、長期停電や物流停止が起こるケースが増えています。
・感染症の拡大
新型コロナウイルスでは、在宅勤務やオンライン授業への迅速な切り替えができるかで対応力に差が出ました。
・サイバー攻撃の増加
システム障害や情報漏えいで業務が止まるリスクが拡大しています。
こうした背景のもと、計画書を整備しておくことが、「いざというときの組織の生命線」となります。
中小企業庁の指針でも、
「従業員とその家族の生命を守り、事業を継続することで顧客と地域経済を守る」
とBCPの目的を強調しています。
BCP事業計画書とは?ひな形を使うメリット
BCP事業計画書の役割と必須項目
BCP事業計画書とは、
自社や自組織のBCPを「誰が見ても分かる形でまとめた公式の文書」 のことです。
災害や事故が発生した際、この計画書をもとに全社員・関係者が同じ手順で動くことで、
重要業務を止めずに継続・早期復旧することができます。
計画書には、少なくとも次のような項目が盛り込まれます。
- 組織情報(責任者・連絡先・拠点一覧など)
- リスク評価と重要業務(守るべき業務とその優先順位)
- 目標復旧時間(RTO)・代替手段(代替拠点や予備人員の確保)
- 緊急時の連絡網・安否確認体制
- 訓練・改善の仕組み(見直し手順、訓練計画)
計画書が整備されていれば、現場の判断がぶれず、経営層から現場まで一貫した対応が可能になります。
ひな形を活用するメリット(効率・抜け漏れ防止・最新トレンド反映)
ゼロから計画書を作ろうとすると、
「どの項目が必須なのか」「記載順序はどうすればいいか」といった悩みが生まれます。
そんなときに役立つのが ひな形(テンプレート) です。
ひな形を活用するメリット
✅ 必須項目が網羅されているため、抜け漏れを防げる
✅ フォーマットが整っているので作成時間を短縮できる
✅ 最新のガイドラインや実務事例を反映したものも多い
✅ 社内で共有・更新しやすい
特に初めてBCP計画書を作成する組織にとって、ひな形は「道しるべ」となります。
BCP事業計画書ひな形の構成と記載ポイント
基本情報(会社概要・責任者・連絡先)
計画書の冒頭には、組織の基本情報を明記します。
災害時に連絡を取りたいが「どこに」「誰に」連絡すべきかが不明では、初動が遅れてしまいます。
- 会社名・所在地・主要拠点の住所
- 代表者・危機管理責任者の氏名と連絡先(電話・メール)
- 緊急時の代替責任者や、各部署の連絡先リスト
ポイント:最新の人事異動や拠点変更を反映し、定期的に見直すことが重要です。
リスク評価・重要業務の特定
想定する計画書の中心となるのが、どんなリスクに備え、何を優先して守るかを明確にする部分です。
(想定されるリスク:地震・水害・火災・感染症・サイバー攻撃など)
各リスクが発生した場合の影響度・緊急度を評価し、対応の優先順位をつける必要があり、
止めてはいけない業務(例:製造ライン、学生対応窓口、緊急診療など)を特定することで、限られた資源をどこに集中させるべきかが見えてきます。
ポイント:中小企業庁のガイドラインでも「業務影響分析(BIA)」の実施が推奨されています。
→ 「どの業務を優先するか」が計画全体の軸になります。
目標復旧時間(RTO)と代替手段の記載方法
RTO(目標復旧時間)を設定することで、復旧の目安を決めます。
あわせて、MTPD(最大許容停止時間)も考慮すると計画がより具体的になります。
例:製造Aライン の場合
RTO:24時間以内
代替手段:別工場での臨時生産、外注先の活用、在宅勤務への切り替え
ポイント:リソース(人・設備・情報)をどのように確保するかを具体的に書き込むと、実務で役立つ計画書になります。
緊急連絡網・安否確認体制の記載ポイント
災害時の混乱を最小限にするため、「誰が誰に、どの手段で連絡を取るか」を明記します。
誰が誰に:緊急時の階層別連絡フロー(本部→各拠点→個人)
どの手段で:一斉連絡ツール(メール、SMS、安否確認システムなど)
ポイント:訓練で実際に使い、改善点を反映させておくと実効性が高まります。
訓練計画・見直し手順の記載ポイント
BCPは作っただけでは意味がないため、計画書内に「どう運用し、どう改善するか」を記しておきます。
- 訓練の頻度(例:年1回の全社訓練、半年ごとの机上訓練)
- 訓練結果をどうフィードバックして計画を更新するか
- 年次レビューの実施や責任者会議のスケジュール
ポイント:計画書の最終ページに「更新履歴」を入れておくと、最新版かどうかがすぐ分かり便利です。
【無料ダウンロード可】おすすめのBCPひな形・テンプレート
中小企業庁のBCPひな形(レベルA・Cなど)
最も代表的で実用性が高いのが、中小企業庁が公開しているBCPひな形です。
中小企業庁「BCP策定運用指針」では、企業規模や成熟度に合わせたテンプレートや業種別のテンプレートも提供されています。
【企業規模や成熟度に合わせたテンプレート】
レベルA:小規模企業向けの簡易版
レベルC:より詳細な標準版(業務影響分析や復旧目標時間などを詳しく記載)
【業種別テンプレート】
製造業向け:製造ラインの代替計画や資材調達の優先度を記載しやすいフォーマット
サービス業向け:顧客対応や予約管理など、業務特性に合わせた項目を盛り込める
教育機関向け:学生・教職員の安否確認やオンライン授業への切り替え手順を反映しやすい
種特化のひな形を活用すれば、自社に必要な要素を抜け漏れなく盛り込みやすくなります。
👉 公開ページ
中小企業庁 BCP策定運用指針
Word・Excel形式のテンプレートがあり、基本項目が網羅されているため初めてでも書き進めやすいのが特徴です。
各自治体が公開するひな形
各自治体も地域特性を踏まえたBCPひな形を配布しています。
たとえば…
大阪府では、「中小企業BCP策定支援ツール」
愛知県では「あいちBCPモデル」
など、自治体ごとに細かいチェックリストや記入例があり、地域特有のリスク(地震・水害など)を反映しやすいのが強みです。
Excel・Wordなど形式別の選び方
多くのひな形は Word形式 か Excel形式 で提供されています。
Word版:文章中心で、社内マニュアルにそのまま組み込みやすい
Excel版:リスト化・数値管理がしやすく、後から更新や集計が簡単
複数のフォーマットを組み合わせて、
「基本計画はWordで、リスク評価や連絡網はExcelで管理」といった運用をする企業も増えています。
ひな形を活用したBCP事業計画書の作成手順
手順①:リスク評価と業務影響分析(BIA)
まずは自社が直面するリスクを洗い出し、その影響を分析することから始めます。
中小企業庁の「BCP策定運用指針」では、これを 業務影響分析(BIA) と呼び、最初のステップとして推奨しています。
想定するリスク:地震・台風・豪雨・火災・感染症・サイバー攻撃 など
各リスクが発生した場合、どの業務がどれくらいの時間止まると致命的かを評価
必要に応じて、各部署や拠点からヒアリングを行い、現実的なデータを集める
ポイント:この段階で「何を守るべきか」を明確にすると、ひな形に記入しやすくなります。
手順②:重要業務・優先度の決定
業務の中から 「絶対に止めてはいけない業務」 を特定します。
例:
製造業 → 基幹ラインの操業、調達業務
教育機関 → 学生への連絡、オンライン授業の実施
サービス業 → 顧客対応窓口、データ保全業務
ポイント:優先度の高い業務から計画書に落とし込みます。
優先度を決める基準(売上への影響度・取引先への影響度など)も明記すると実務で活きます。
手順③:代替拠点・代替手段の検討
重要業務を守るために、「もし拠点やシステムが使えない場合どうするか」を考えます。
代替拠点:別支社・提携先・サテライトオフィス
代替手段:クラウドサービスや外部委託、在宅勤務
予備資源:予備人員・予備設備・バックアップ回線
ひな形には、これらの代替案を具体的に記載する欄が用意されていることが多いので、検討結果をそのまま記入できます。
手順④:計画書に落とし込み、社内周知
リスク評価や代替手段を整理できたら、ひな形を使って計画書にまとめます。
WordやExcelのフォーマットに、組織情報・重要業務・復旧手順を記載し、
完成したら全社員が閲覧できるように社内共有します。(イントラネット・マニュアル配布など)
部署ごとに簡易マニュアルを作ると現場が動きやすくなります。
手順⑤:訓練・更新サイクルを組み込む
最後に、計画を実際に動かすための運用計画を加えます。
- 年1回以上のBCP訓練を実施する計画を盛り込む
- 訓練後のフィードバックをどのように計画書へ反映するか記載
- 更新履歴を残し、最新版を常に全社員が確認できる状態にする
👉 これで、ひな形を活用した実践的なBCP事業計画書が完成します。
記載時のよくある失敗と改善のヒント
テンプレートを埋めただけで実践できない
ひな形を活用すると短時間で計画書を作れますが、
「書いただけ」で終わってしまうケース が少なくありません。
現場で動ける計画になっていないと、いざというとき役に立ちません。
改善のヒント:
・記載後、関係者と一緒に「実際に動かすシミュレーション」を行う
・書類にある手順が現場で実行可能か、訓練で検証する
・記入担当者だけでなく、各部署の責任者と共有・調整する
拠点や部署ごとの状況差を反映できていない
本社の計画をそのままコピーしただけでは、
各拠点や部署の実情に合わず動かせない という事態も起こります。
改善のヒント
・各拠点ごとにミーティングを実施し、独自の事情をヒアリング
・「共通の基本計画」と「拠点別の実行計画」の二層構造にする
・地域特性(地震・水害・停電リスクなど)を個別に盛り込む
担当者交代で計画書が形骸化する
BCP担当者が異動・退職すると、
誰も内容を理解していない計画書だけが残るケースもよくあります。
改善のヒント
・計画書内に「責任者・後任引き継ぎフロー」を明記
・定期的な研修や訓練で、複数名が内容を理解するようにする
・更新履歴を残し、最新版を共有サーバーで管理する
BCP事業計画書の最新動向と見直しポイント
テレワーク・クラウド対応を盛り込む方法
近年のBCPでは、テレワークやクラウドサービスをどう活用するかが重要な要素になっています。
内閣府「事業継続ガイドライン(2023年改訂)」でも、
「情報システムやクラウドを活用した分散化・テレワーク体制は、事業継続に有効」
と記載されています。
計画書への盛り込み例
・在宅勤務時の業務フローや連絡ルールを具体的に記載
・クラウドストレージへの重要データのバックアップ手順
・VPN・二段階認証など、セキュリティ確保の方法
こうした記載があれば、物理的なオフィスが使えない状況でも業務を続けやすくなります。
感染症対策や気候変動リスクを記載するコツ
これまで地震や火災を中心に想定していたBCPも、
感染症や気候変動への対応を計画書に盛り込む必要が出てきています。
感染症対策の記載例
・感染拡大時の出勤制限や分散勤務の実施手順
・消毒・換気など職場での衛生管理基準
・代替要員確保や業務優先順位の再調整方法
気候変動リスクの記載例
・豪雨・猛暑による停電や設備被害を想定した代替策
・電力供給停止時のバックアップ電源確保の手順
・熱中症リスクに対応した勤務時間調整
サプライチェーン・協力会社との連携項目
BCP計画書は自社内だけで完結せず、取引先・協力会社と連携する項目も入れることで実効性が高まります。
記載ポイント
・主要取引先・調達先の緊急連絡先リスト
・協力会社との「相互復旧支援協定」や覚書の有無
・物流や部品供給が止まった場合の代替ルート
これらを盛り込むことで、組織の垣根を越えた事業継続が実現しやすくなります。
災害時に確実な安否確認を行うには、信頼できる仕組みが不可欠です。
ANPIC(アンピック)なら、誰でも簡単に使えるシステムと手厚いサポートで、初めての導入でも安心してお使いいただけます。
- 100万人超が利用
- 直感操作で導入もスムーズ
- 専任スタッフが全面サポート
- 産学連携で実現した手頃な価格
ANPICでは、実際の管理画面を操作しながら機能や使い方を体験できる無料体験版をご用意しています。 体験中にご不明な点があれば、無料でサポートも受けられるので、安心してお試しいただけます。
まとめ|ひな形を活用して、自社に合ったBCP事業計画書を作ろう
BCP(事業継続計画)は、災害や事故、感染症、サイバー攻撃といった不測の事態においても、
重要な業務を中断させず、または短期間で再開させるための組織の「生命線」です。
その実践のために欠かせないのが 「BCP事業計画書」 であり、
計画書を整備しておけば、いざというとき全員が迷わず同じ手順で動くことができます。
しかし、ゼロから作るのは大変です。
そこで役立つのが、国や自治体が公開している ひな形(テンプレート) です。
ひな形を活用すれば、
✅ 必須項目の抜け漏れを防ぎ
✅ 作成時間を大幅に短縮でき
✅ 最新のガイドラインを反映した実践的な計画書を作ることができます。
本記事で紹介したように、
・中小企業庁や東京都などが無料で提供するテンプレート
・業種・業態ごとの具体的なフォーマット
・記載ポイントや訓練・見直しのヒント
を活用すれば、初めての担当者でもしっかりとしたBCP事業計画書を作成できます。
大切なのは「作って終わりにしないこと」。
計画書を作成した後は、定期的に訓練・見直しを行い、実際に動かせる計画へと進化させていきましょう。
▶️ まずは公的機関のひな形をダウンロードして、自社に合わせたBCP計画書づくりをスタートしてください。

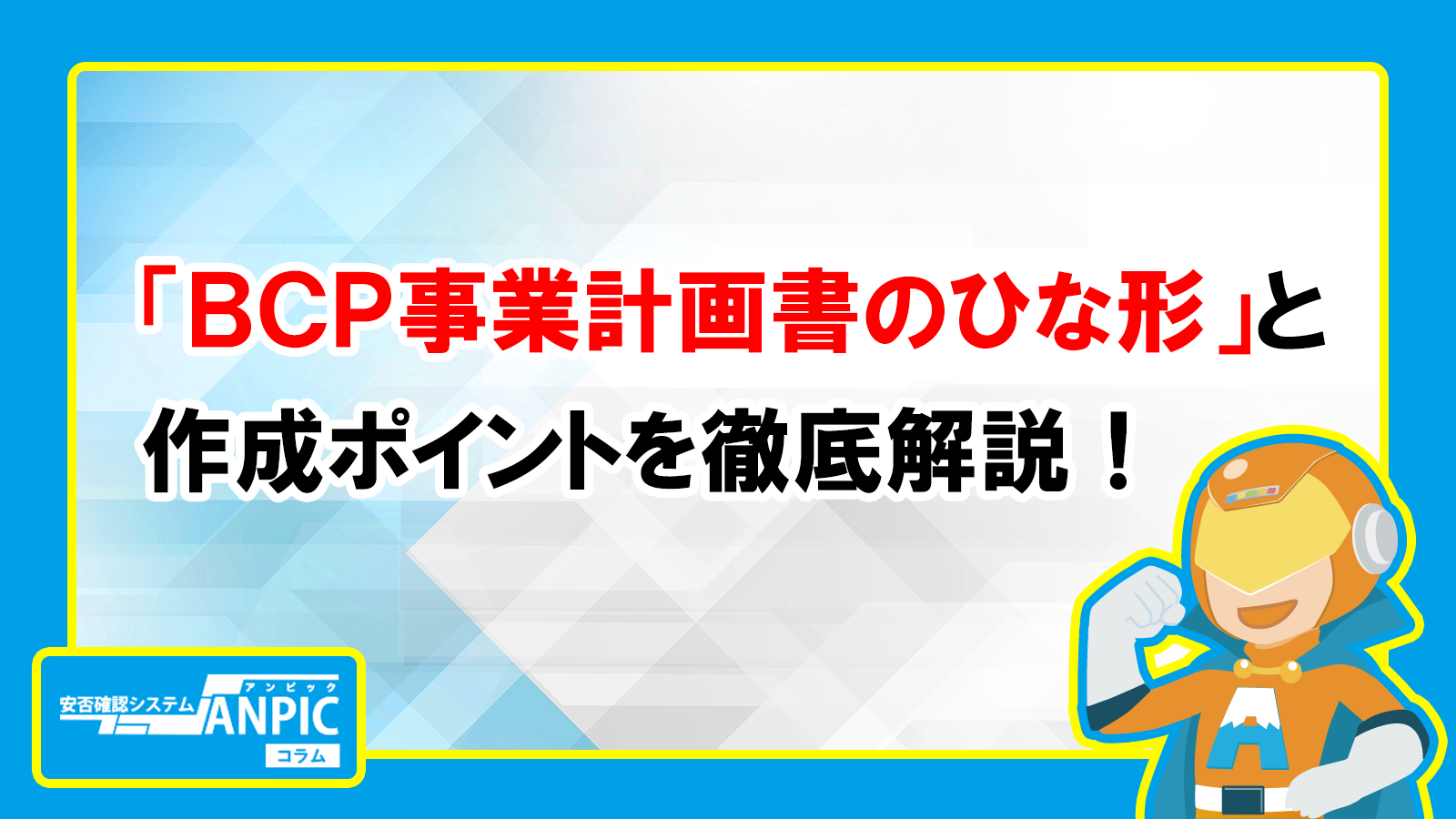


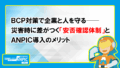
コメント