災害時に確実な安否確認を行うには、信頼できる仕組みが不可欠です。
ANPIC(アンピック)なら、誰でも簡単に使えるシステムと手厚いサポートで、初めての導入でも安心してお使いいただけます。
- 100万人超が利用
- 直感操作で導入もスムーズ
- 専任スタッフが全面サポート
- 産学連携で実現した手頃な価格
ANPICでは、実際の管理画面を操作しながら機能や使い方を体験できる無料体験版をご用意しています。 体験中にご不明な点があれば、無料でサポートも受けられるので、安心してお試しいただけます。
はじめに:災害時、“安否確認の遅れ”が事業継続を止める
地震、台風、豪雨、感染症など、災害リスクは年々深刻化しており、「いつか起きる」ではなく「いつでも起きうる」という前提で対策を講じる必要があります。
中でも最も重要なのが、“災害直後の初動対応”であり、その鍵を握るのが、従業員・学生の「安否確認」です。
■ 安否がわからないと、何も始まらない
災害発生直後、企業・学校が最初に行うべきことは「人の無事の確認」です。
・誰が無事なのか
・誰と連絡が取れないのか
・どの拠点に被害があるのか
この情報がなければ、出社指示・在宅対応・拠点封鎖・再開判断など、あらゆる意思決定が止まってしまいます。つまり、「安否が確認できない=事業を動かせない」という状態になるのです。
■ 安否確認の遅れがもたらす3つのリスク
| リスク | 説明 |
| ❶ 業務停止が長引く | 状況が把握できず、出勤や業務再開の判断が遅れる |
| ❷ 社内外の信頼低下 | 顧客・取引先に「何も対応できていない会社」と見なされる |
| ❸ 社員・学生の不安増大 | 対応が遅れたことにより、混乱・不満・退職にも繋がる可能性 |
■ 安否確認は“早さ”と“確実さ”が命
電話や手動のメール連絡では、時間がかかる・届かない・集計ができないといった問題が発生しがちです。そのため、近年では「安否確認システム」の導入が、企業や教育機関で加速しています。
特に次のような仕組みを持つシステムであれば、初動対応のスピードを一気に上げることができます
・地震情報と連動した自動通知
・メールやLINEによる複数通知
・ワンクリック回答+自動集計
・代理回答機能
■ この記事の目的
本記事では、この「安否確認」を軸に、
・災害時に企業・学校がとるべき確認手段
・手動連絡とシステム活用の違い
・実際に役立つシステム選定ポイント
などを具体的かつ実践的に解説していきます。災害は“起きてから考える”では手遅れです。今こそ、「確認できる体制づくり」が必要です。
安否確認の目的と重要性
災害発生直後における安否確認は、単なる“出欠確認”ではありません。組織として人命を守り、事業の継続判断を行うための「情報基盤」です。ここでは、安否確認の目的と、企業や学校にとってどれほど重要なものなのかを、3つの観点から整理します。
1. 人命を守るための最優先行動
地震や台風などの災害が発生した際、従業員・学生が無事かどうかを確認することは、何よりも優先すべき対応です。
災害直後は、
・出勤・登校途中に巻き込まれていないか?
・拠点で孤立・閉じ込められていないか?
・家族が被災し、身動きが取れない状態ではないか?
といった情報を早急に把握する必要があります。
特に企業では、社員の命に対する配慮ができていない=社会的信頼を損なうことに直結します。
2. 事業継続判断の基礎情報になる
BCP(事業継続計画)において、初動で重要なのが「人的リソースの状況把握」です。
・どの部署の何割が出社・在宅勤務可能か?
・被災地域の拠点で業務を再開できるか?
・代替人員や遠隔対応に切り替える必要があるか?
これらは、安否情報なしには判断できません。
つまり、安否確認は単なる“安否の有無”にとどまらず、「事業を止めないための判断材料」そのものなのです。
✅ 3. 社内の安心感と組織の信頼を高める
災害時の安否確認は、従業員や学生にとっても大きな意味を持ちます。
・「すぐに会社・学校が状況を確認してくれた」
・「対応が早くて安心できた」
・「通知が来ることで、自分の行動指針が明確になった」
このような体験は、組織への信頼・帰属意識の向上にも繋がります。
逆に、何の確認もなく放置された場合、不安や不満、離職のリスクすら生まれます。
🔎 まとめ:安否確認は“人を守り、組織を動かす”行為
災害時の安否確認は、
・人命保護
・事業継続判断
・社内外の信頼維持
という3つの観点から、組織にとって不可欠な行動です。
「確認できなかったから、動けなかった」そんなことがないよう、体制と仕組みの整備が今まさに求められています。
災害時に使える安否確認の方法4選【手段別】
災害が発生した際、すぐに安否を確認することは非常に重要です。
しかし、「どうやって確認するか?」の手段によっては、スピード・正確性・信頼性に大きな差が生じます。
ここでは、現場でよく使われる代表的な4つの安否確認方法を、メリット・デメリットを交えて解説します。
方法①:電話連絡網(手動方式)
概要:上司・リーダーが下位メンバーに連絡し、それをまた次の人へと伝達していく“ピラミッド型”の連絡手段。
メリット:
・システムが不要で今すぐ始められる
・会話で詳細を確認できる
デメリット:
・時間がかかる(人数が多いほど非効率)
・つながらないと全体が止まる
・担当者に負荷が集中する
・情報の集計・可視化が困難
向いている組織:
・従業員10人未満の小規模企業や地域活動団体
方法②:メール・LINEグループ・チャットツール
概要:メーリングリストやLINE、Slack、Teamsなどで一斉送信し、メンバーの安否回答を求める方法。
メリット:
・普段使っているツールを活用できる
・スマホから手軽に回答できる
デメリット:
・見逃し・通知オフなどで届かないことも
・回答を集計するのに手間がかかる
・業務とプライベートが混在していると混乱を招く
向いている組織:
・社内に普段からLINE・Slack等の習慣がある企業
・一時的な訓練や補助的な手段として
方法③:Excel・Googleフォームなどの自主報告フォーム
概要:回答フォームやExcel入力表を作成し、URLを共有して入力してもらうスタイル。
メリット:
・初期コストなしで作成可能
・記録が残る
デメリット:
・通知手段(メール・チャット)と別管理になる
・集計・確認に時間がかかる
・入力漏れ・二重入力の可能性あり
向いている場面:
・訓練用の簡易確認、社内施策の試験導入段階
・専任担当者が少ない組織にはやや不向き
方法④:専用の安否確認システムを使う(推奨)
概要:災害時に自動で一斉通知・安否確認・集計を行うクラウド型のシステム。多くがLINE・アプリなど複数通知手段に対応。
メリット:
・地震情報などと連携して自動通知が可能
・ワンクリック回答で誰でも使える
・回答状況をリアルタイムで管理画面に表示
・部署別・拠点別に自動集計されるため指示出しがスムーズ
・災害以外にも「健康報告」「出勤可否確認」など平時利用も可能
デメリット:
・月額料金がかかる
・初期登録など導入準備が必要(ただしサポートあり)
向いている組織:
・中小企業〜大企業全般
・拠点・部署が複数に分かれている場合
・教育機関(大学・専門学校)など広域な管理が必要な組織
🔚 まとめ:スピードと信頼性を両立するには「システム化」が最適解
| 方法 | 即時性 | 信頼性 | 負荷 | 規模対応 |
| 電話連絡網 | × | △ | 高 | 小規模向き |
| メール・LINE | △ | △ | 中 | 中規模向き |
| フォーム | △ | △ | 中 | 限定的 |
| 安否確認システム | ◎ | ◎ | 低 | あらゆる規模に対応 |
災害時は1分1秒を争う状況です。
どんなに優れた体制でも、「情報が集まらない」「把握できない」状態では機能しません。
そのため、スピード・正確性・集計性を同時に満たす 専用の安否確認システム導入が、もっとも現実的かつ効果的な選択です。
安否確認システムのメリットとは?
安否確認を「手動」や「LINEグループ」「電話」で済ませている企業・学校も多い中、近年導入が進んでいるのが専用の安否確認システムです。
「人力では限界がある」「届かない・返ってこない・集計できない」
こうした課題を一気に解決するのが、ITによる自動化と可視化です。
ここでは、安否確認システムを導入することで得られる4つの大きなメリットを紹介します。
1. 一斉配信+マルチチャネル通知で“確実に届ける”
安否確認システムは、登録された全ユーザーに対して一斉に通知を送信できます。
加えて、以下のような複数の通信手段に対応しているため、届かないリスクを限りなくゼロに近づけることが可能です。
・メール通知
・LINE通知
・スマートフォンアプリ通知
災害時は予期せぬ通信障害が発生する可能性があるため、 複数の通知先を設定できることが非常に重要です。
2. ワンクリック回答・ログイン不要で“誰でも使える”
操作のシンプルさも、安否確認システムの大きな強みです。
・通知文に含まれるURLをクリック
・「無事です」「ケガあり」などの選択肢をタップ
・回答完了!
という“1分以内で完了する操作設計”がほとんどで、年齢・ITリテラシーを問わず使いやすいのが特徴です。
さらに、システムによってはアカウントログイン不要で回答可能なものも多く、初動時の混乱を防ぐことができます。
3. 自動集計・リアルタイム表示で“初動判断が速くなる”
安否確認システムは、ただ送るだけでなく、回答をリアルタイムで可視化・集計してくれます。
・回答率(%)
・回答内容別の人数集計
・未回答者の一覧
・地域別・部署別の状況表示
これらを瞬時に把握できるため、「誰に連絡がついていないか」「誰が出勤できるか」「被災地域はどこか」といった初動判断が早くなります。
4. 災害以外にも“日常業務に活用できる”
安否確認システムは、災害時だけでなく平常時の情報収集・連絡ツールとしても活用できます。
活用例:
・体調報告・出社可否の確認(感染症対応)
・テレワーク中の業務状況報告
・災害訓練や避難訓練への出欠確認
・台風接近時の「出社/在宅判断」の確認
つまり、「備え」だけでなく「日常活用」も可能なインフラとして導入できるのが特徴です。
💡 補足:ANPICの場合(システム例)
ANPIC(アンピック)は、災害対策に特化した安否確認システムで、次のような特徴があります。
・LINE通知+メール通知+専用アプリ通知を無料標準搭載
・ワンクリック回答、代理回答も対応
・月額5,130円〜でコスト負担も軽い
・教育機関・中小企業での導入多数
・訓練メッセージテンプレート、マニュアル提供、初回説明会・初回ユーザー代行登録等のサポートも無料
まとめ:安否確認は“システムで備える”時代へ
災害時の混乱を最小限に抑え、
・情報の早期収集
・初動判断の迅速化
・社員・学生の不安の軽減
・社会的責任の履行
を実現するには、手作業に頼らない仕組み化=システム導入が不可欠です。
「確認できるか」ではなく、「確認できる仕組みがあるか」が、災害対応の分かれ道になります。
災害別に見る安否確認のポイント
安否確認と一口にいっても、災害の種類によって適したタイミング・手段・確認項目は大きく異なります。
ここでは、代表的な災害ごとに、安否確認のポイントや備えるべき体制の違いを整理します。
地震発生時|即時対応&自動化がカギ
特徴:
・予告なく突然発生
・広範囲かつ瞬間的な被害
・通信インフラや交通機関に影響が出やすい
安否確認のポイント:
・地震情報と連動した自動通知が最も有効
・回答はワンクリック・ログイン不要にし、スマホからすぐに返せるように
・通信障害時に備えたメール・LINE等の多重通知が重要
備えのコツ:
・訓練では“出社中・通勤中・帰宅中”など、時間帯別にシナリオを分けて実施
・拠点別や部署別の集計機能で、迅速な判断体制を構築する
台風・大雨・洪水|事前の通知と事後確認が重要
特徴:
・発生予測が可能(事前の警報あり)
・長時間にわたり影響が出る(出社不可・帰宅困難)
・地域によって被害差が大きい
安否確認のポイント:
・前日〜当日の朝に通知・出勤可否の確認を行う
・通知はスマホとPCの両方で見られる媒体(LINE+メール、アプリ+メール)を活用
・被害の程度によっては、家屋浸水・通勤不能などの自由記述欄も役立つ
・事後には安否確認+通勤・自宅の状況確認も実施
備えのコツ:
・通知内容に「これは台風接近による確認です」と災害種別を明記
・安全配慮義務として、出社停止判断の判断材料にもなる
大雪・交通障害|出社判断と代替勤務対応
特徴:
・交通機関の停止・遅延が中心的な影響
・首都圏では年数回発生し得る
・命の危険は低くても業務継続に大きく影響
安否確認のポイント:
・出社前に「本日出社可否・在宅勤務可否」を一斉確認
・対応パターン:■出社可能
■在宅勤務可
■欠勤希望(理由あり)
・回答フォームを設け、自動集計できるシステムが望ましい
備えのコツ:
・事前に社員に「雪の日の連絡方法」マニュアルを配布
・BCPとして在宅勤務・業務シフト切替えの指示テンプレートも準備
感染症・パンデミック時|継続的な体調報告が重要
特徴:
・交通機関の停止・遅延が中心的な影響
・首都圏では年数回発生し得る
・命の危険は低くても業務継続に大きく影響
安否確認のポイント:
・出社前に「本日出社可否・在宅勤務可否」を一斉確認
・対応パターン:■出社可能
■在宅勤務可
■欠勤希望(理由あり)
・回答フォームを当日限定で設け、CSVで自動集計できるシステムが望ましい
備えのコツ:
・事前に社員に「雪の日の連絡方法」マニュアルを配布
・BCPとして在宅勤務・業務シフト切替えの指示テンプレートも準備
感染症・パンデミック時|継続的な体調報告が重要
特徴:
・長期的な対応が必要(1日で完結しない)
・地域差ではなく全社的な体制が必要
・対象は本人だけでなく、家族・同居者も関係
安否確認のポイント:
・毎日の体調報告(例:発熱・咳・濃厚接触有無)をフォームで入力
・本人だけでなく「家族の健康状態」も記述欄に含めるとよい
・アンケート機能付きの安否確認システムが活躍
備えのコツ:
・定型回答+自由記述欄で柔軟な情報収集
🧩 まとめ:災害種別に応じた“確認スタイルの設計”がカギ
| 災害 | タイミング | 通知方法 | 確認項目 |
| 地震 | 即時 | 自動通知(地震連動) | 安否・位置・被災状況 |
| 台風 | 事前・事後 | 手動通知(前日/当日) | 出社可否・被害状況 |
| 大雪 | 当日朝 | 手動通知 | 出社可否・在宅勤務対応 |
| 感染症 | 継続 | 日次通知(アンケート形式) | 体調・家族状況 |
すべての災害に共通するのは、
「いつ、だれに、どうやって、何を聞くか」をあらかじめ定めておくこと。
そのためには、安否確認システムを「柔軟に設定・活用できる設計」にすることが大切です。
安否確認システム導入時のチェックポイント
「安否確認システムを導入しよう」と決めたものの、いざ選ぼうとすると「機能が似ていて違いがわからない…」「うちの会社や学校に合うかわからない…」そんな声をよく聞きます。
安否確認システムは“いざという時に確実に機能するかどうか”が最重要。
導入前にしっかりと確認すべき5つのチェックポイントをご紹介します。
1. 通知手段が複数あるか(マルチチャネル対応)
災害時は、メールだけでは不達・見逃しのリスクがあります。
チェックポイント:
✔️ LINE通知に対応しているか?
✔️ スマホアプリ通知があるか?
✔️ 通知手段をユーザーごとに選択可能か?
👉 複数の通知手段に対応していれば、届かないリスクを大幅に減らせます。
2. 操作が簡単か(誰でも使えるか)
非常時は誰もが緊張状態にあります。難しい操作は回答率の低下に直結します。
チェックポイント:
✔️ ログイン不要で回答できる?
✔️ 回答はワンクリックで済む?
✔️ 高齢者やスマホに不慣れな人でも使える設計か?
✔️ 回答ページはシンプルで直感的に操作可能か?
👉 「1分以内で回答できるか?」を基準に選ぶと◎。
3. 集計・可視化の機能があるか
確認だけでなく、集計・判断がスムーズにできるかどうかもカギです。
チェックポイント:
✔️ 回答率/未回答者がリアルタイムで表示される?
✔️ 拠点別・部署別に回答状況を分類できる?
✔️ CSVで報告用データを出力できる?
✔️ 代理回答・再通知など、回答フォロー機能はあるか?
👉 「状況をすぐに“見える化”できる」ことが、初動対応の質を決めます。
4. コストと運用負担が現実的か
コストが高すぎたり、担当者が使いこなせないと継続できません。
チェックポイント:
✔️ 初期費用は無料 or 最小限か?
✔️ 月額は固定制 or 従量制?(自社に合った課金モデルか)
✔️ 管理画面の操作性はよいか?
✔️ 担当者が兼務でも無理なく運用できるか?
👉 「価格と操作性のバランス」を必ず見ておきましょう。
5. 導入・訓練の支援体制は整っているか
初めての導入では、サポートの有無が成否を分けます。
チェックポイント:
✔️ 無料トライアルや事前デモができる?
✔️ 操作マニュアル・訓練テンプレートがある?
✔️ 導入時のメール文例や周知資料は提供される?
✔️ カスタマーサポート窓口は用意されている?
👉 “始めやすく・続けやすい”環境があるかどうかが重要です。
📝 まとめ:安否確認システム選びの6つの視点
| 観点 | 確認すべきポイント |
| 通知手段 | 複数の通知手段に対応しているか |
| 操作性 | 誰でも迷わず使える設計か |
| 可視化 | 回答をリアルタイム集計・表示できるか |
| 自動化 | 災害と連動して即時通知できるか |
| コスト | 費用と社内リソースのバランスが合うか |
| サポート | 導入〜運用まで支援があるか |
💡 ANPICなら、すべてのチェック項目を満たします
✔️ LINE/メール/アプリ対応のマルチ通知
✔️ ワンクリック回答&ログイン不要設計
✔️ 拠点別・部署別の自動集計と可視化
✔️ 地震情報に自動連動
✔️ 月額5,130円~
✔️ 訓練支援、操作マニュアルの提供、初回説明会や初回ユーザー代行登録などの無料サポート
ANPICを活用した災害時対応の実例紹介
安否確認システムは「万が一のとき」の備えであると同時に、実際の災害時に“使えるかどうか”が最大の評価ポイントです。
ここでは、実際にANPICを導入している企業・学校が、災害発生時にどのように活用し、どんな効果が得られたのかを、具体的な事例とともにご紹介します。
事例①:日常使いや訓練を継続することで、回答率が向上し防災意識の定着にもつながった
背景:
社員の安否確認には災害用伝言ダイヤルの使用を検討していたが、「繋がらない」「一方行の連絡のみ」という点に不安を感じていた。
ANPIC導入後の対応:
・日常時の連絡手段としてもANPICを使用
・携帯電話やメールを使わない社員には代理報告機能を活用し、安否情報を一元管理
効果:
・社内で「アンピック」という言葉が定着し、防災意識が向上
・定期的な訓練の実施により回答率が向上し、店舗・施設単位での理解度も向上
・安否情報の一元管理と自動集計により、災害時の状況把握が迅速かつ容易に
詳細はこちら
事例②:東日本大震災の教訓からANPICを導入し、確実な安否確認と迅速な対応を実現
背景:
東日本大震災を機に社員の安全確保と迅速な安否確認の重要性を痛感した。
ANPIC導入後の対応:
・年2~3回訓練を実施し、未報告者には個別指導を行うことで訓練精度を向上
・「災害時はANPICで報告」という行動習慣を社員に定着
効果:
・実際の地震発生時(震度5以上)にも、従業員の安否を迅速に確認しスムーズな運用を実現
・訓練では1時間以内に回答率100%を達成
・出社可否の状況が可視化されたことで、業務再開の判断が迅速になった
詳細はこちら
事例③:学生の入れ替わりが激しい環境の中、緊急連絡網の維持管理と安否確認の確実性を両立
背景:
学校では毎年多数の入退学があるため、名簿の更新が難しく、私的メールアドレスを利用した緊急連絡では到達率や応答率の低下が課題となっていた。
ANPIC導入後の対応:
・学校特有の複雑な組織階層(学部・研究科・事務部など)に柔軟に対応できる体制を構築
・学内の既存データベースと連携し、名簿更新作業の自動化・効率化を実現
・所属組織を超えた要員のグループ(例:防災対策委員)登録を活用し、実務的な運用がスムーズに
効果:
・全学規模での緊急連絡網の信頼性と即応性が大幅に向上
・名簿の更新作業に伴う管理負担を大幅に軽減
・継続的な訓練と情報管理により、災害時の対応力と実践的な運用精度が向上
詳細はこちら
💡 導入現場の声から見える、ANPICの“選ばれる理由”
| 特長 | 現場評価の声 |
| LINE通知が無料 | 「学生・社員の回答率が高くなった」 |
| ワンクリック回答 | 「誰でもすぐに対応できる設計」 |
| CSV出力対応 | 「管理資料の作成が圧倒的にラク」 |
| 平常時利用OK | 「感染症・出勤確認にも転用できた」 |
| 業界トップクラスの低価格 | 「限られた予算内で運用するができている」 |
| 充実した無料サポート | 「導入時に初回ユーザー登録や初回説明会のサービスがあり、担当者の負担を軽減できた」 |
| シンプルで直感的に使いやすいデザイン | 「初めて使った社員も迷わず操作ができ、スムーズに安否確認が完了した」 |
📝 まとめ:実績でわかる、“備えていてよかった”という実感
・実際の災害時に機能しなかった仕組みは「備え」とは言えない
・ANPICは、あらゆる災害パターン・組織形態にフィットする柔軟性と信頼性を備えている
・「安否確認=義務」から、「安否確認=守る力」へ
災害時に確実な安否確認を行うには、信頼できる仕組みが不可欠です。
ANPIC(アンピック)なら、誰でも簡単に使えるシステムと手厚いサポートで、初めての導入でも安心してお使いいただけます。
- 100万人超が利用
- 直感操作で導入もスムーズ
- 専任スタッフが全面サポート
- 産学連携で実現した手頃な価格
ANPICでは、実際の管理画面を操作しながら機能や使い方を体験できる無料体験版をご用意しています。 体験中にご不明な点があれば、無料でサポートも受けられるので、安心してお試しいただけます。
まとめ:災害時に“迷わず動ける”体制づくりを
災害は、いつ、どこで起きるかを正確に予測することはできません。
だからこそ、「もしも」に備えておくことが、組織にとって最も重要なリスク対策です。
そしてその中核を担うのが、安否確認の仕組みです。
🚨 初動対応の“数分の差”が命運を分ける
地震、台風、水害、感染症…。どんな災害であっても共通するのは、最初にやるべきは人の無事の確認です。
・社員や学生がどこにいて、無事かどうか
・出社できるのか、支援が必要か
・拠点の被害状況はどうか
こうした情報が「正確に、早く、確実に」集まらなければ、業務継続はおろか、安全確保すらままなりません。
🧩 安否確認=「仕組み」でやる時代へ
従来の電話連絡網やメール手動送信では、どうしても限界があります。
・通知が届かない
・集計に時間がかかる
・担当者に負荷が集中する
・回答状況をリアルタイムで把握できない
これらの課題を解決するのが、安否確認システムです。
特に ANPIC のようなシステムなら、
・地震発生時の自動通知
・複数の通知手段(LINE、メール、専用アプリ)
・ワンクリック回答・代理回答
・管理画面でリアルタイムに状況を把握
・訓練・日常活用もできる汎用性
・担当者の負担を軽減する充実したサポート
といった機能によって、災害時の「迷わず動ける」体制づくりが可能になります。
🛡️ 組織を守るのは、事前の準備と判断の速さ
災害に強い組織とは、「一斉に正しく動ける仕組みを平時から整えている組織」です。
安否確認は、もはや“有事の手段”ではなく、日常業務の一部として備えるべきインフラと言えるでしょう。
📥 次の一歩へ
「災害が起きたら何をすべきか」ではなく、「起きた時に“仕組みで対応できるか” が、組織の責任と信頼を決定づけます。
【無料】ANPIC資料請求はこちらから:https://www.anpic.jp/contact/
【無料】オンラインデモのご希望はこちらから:https://www.anpic.jp/trial/

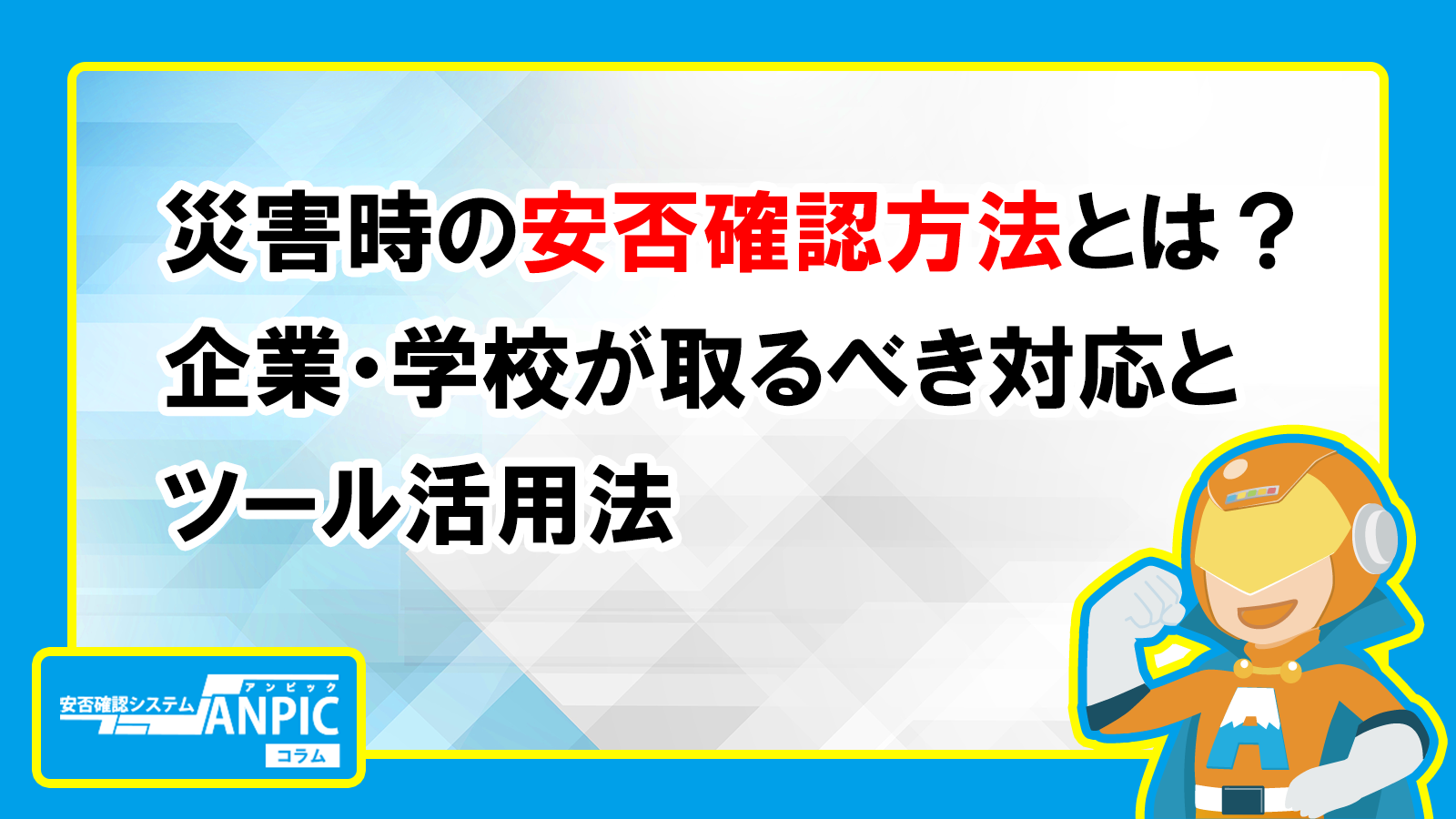

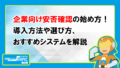
コメント